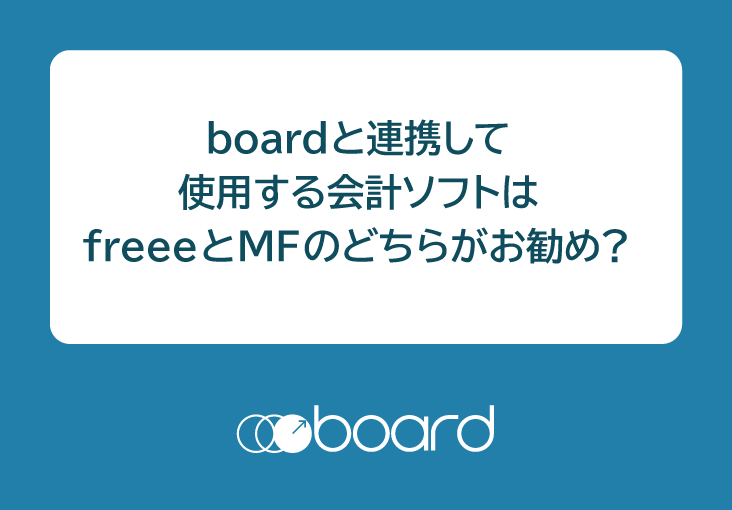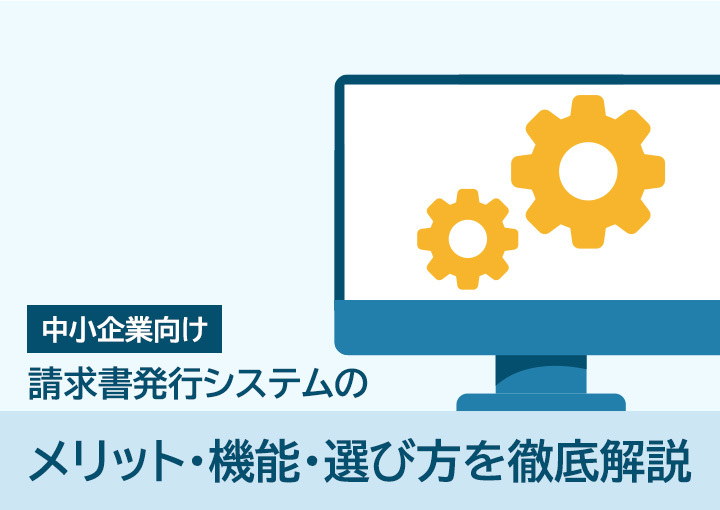多くの中小企業では、人手が足りず日々の業務に追われている状況が続いています。業務設計士としてさまざまな企業の業務を見てきましたが、改善の余地がまったくないという企業は、基本的に存在しません。トヨタ生産方式の基礎を築いた大野耐一氏も著書の中で「どんな現場でも細かく観察すれば必ずムダがある」と述べています。観察する際は、単に現場を眺めるだけではなく、全体像を捉え、各部分がどのような役割や機能を持っているのかを理解することが重要です。
こうした考え方は大企業だけでなく、中小企業にも当てはまります。改善は施策を実施すること自体が目的ではなく、実際に業務効率を少しでも上げることに意味があります。だからこそ、最初の一歩をどこに置くかが重要です。本記事では「どこから始めるか」「どこに目を向けるか」という観点を通して、業務改善の入口を整理していきます。
税理士、業務設計士、リベロ・コンサルティング代表
金融のシステム企画部門、会計事務所、数社のスタートアップのバックオフィスを経て、独立。
既存の業務やシステムの使用方法を徹底的にヒアリングしながら、最適な業務フローとシステムの構成を設計し、業務からシステムまで再構築の実績多数。
業務設計の支援を手がけるリベロ・コンサルティング代表をメインで活動中。
よくある「間違った入口」
業務改善を考えるときに、ついやってしまいがちなアプローチがあります。
1つ目は、とにかく自動化などの効率化をするためのツールを探してしまうことです。「自動化ができれば工数が大幅に減るだろう」と考えがちですが、業務の流れを整理しないままツールを導入すると、結局使いこなせず、現場の負担が増えることにもなりかねません。最近ではAIやAIエージェントの活用が注目されていますが、こちらも同じです。業務の整理や設計を飛ばして導入しても、期待した成果は得られず、むしろ混乱を生む可能性があります。
2つ目は、担当者の不満を解消するために改善に着手するというケースです。もちろん現場の声は重要ですが、強い不満がある部分が必ずしも業務全体にとって改善効果が高いとは限りません。業務改善の結果として担当者がラクになることはありますが、それ自体を目的にしてしまうと部分最適にとどまってしまいます。全体の流れの中でボトルネックになっている部分を見極めることが大切です。
3つ目として、紙やハンコを廃止して、ペーパーレス化することをゴールとして設定するアプローチにも注意が必要です。電子帳簿保存法の改正などにより、ペーパーレス化自体は進めやすくなりましたが、紙の書類があることで業務の流れや状況を把握できていたというケースもあるでしょう。業務の流れを整理しないまま、「紙をなくす」ことだけを目標に定めると、前後の業務とのつながりが見えにくくなり、ミスや重複が発生しやすい状況を作ってしまいます。本来のゴールは、紙をなくすこと自体ではなく、その結果として業務全体の流れをスムーズにすることであるはずです。
このように、業務改善を進めるには準備と調査が欠かせません。ツール導入やペーパーレス化はあくまで手段であり、目的ではないのです。
結局のところ、どんなに立派な施策やツールを導入しても、入口を間違えると改善活動は空回りしてしまいます。ここまで見てきた誤った始め方を避けるために、次は「どこから着手するか」という視点で考えていきましょう。
どこから着手するかの見極め方
業務改善を効果的に進める上では、「どこから手を付けるか」を冷静に見極めることが欠かせません。思いついた順や声の大きさで決めてしまうのではなく、客観的な基準で優先順位を付ける必要があります。
「効果」に注目する
着手すべきポイントを考えるとき、まず注目したいのは、業務量が多くて担当者の負担が大きい部分です。繰り返し作業が多かったり、時間がかかる業務は「回数×所要時間」の積が大きく、短縮効果が累積しやすいため、改善効果が出やすい領域と言えます。毎月繰り返す業務であれば、改善の効果をすぐに確認できるため、継続的に取り組みやすい点も特徴です。
また、少しの改善でも成果を実感しやすいことは、「標準化」に向けて大きな後押しになります。標準化とは、業務の手順やルールを統一し、誰が担当しても同じ成果が得られるようにすることです。標準化が進むと業務のばらつきが減り、引き継ぎや教育が容易になり、改善を持続させやすくなります。
たとえば、勤怠管理や給与計算のように毎月繰り返す処理を改善し、効率の良い方法で標準化すると、入力ミスが減り、担当者の拘束時間は大幅に短縮されます。事務作業は時間をかけたからといって成果が上がるものではありません。重要なのは、同じ成果を安定的に、短い時間で出せるようにすることです。
次に注目すべきは、顧客や売上に直結する業務です。とくに受注から請求、入金確認といったプロセスは企業の資金繰りに直結するため、ミスや遅延があると、経営への影響も大きくなります。さらに契約管理や請求処理といった売上に関わる業務は、一度の不備が取引先との信頼関係に影響しやすく、経営リスクにもつながります。そのため、売上に関わる業務の改善は、リスクを未然に防ぐという視点で、経営層も含めて優先的に取り組む必要があるのです。
「実行しやすさ」に注目する
ここまでは「効果」を軸に話を進めてきましたが、業務改善に初めて着手する際はもう1つ、「実行しやすさ」という軸も掛け合わせて見ていくことが重要です。どんなに高い効果が見込まれるものであっても、実行までのハードルが高い場合(コストが高い、時間がかかる、関係者が多いなど)は、最初に手を付ける対象として不向きです。効果が高く、なおかつ実行しやすいものから取り組むことで、小さな改善の成功体験を積み重ねやすくなります。その積み重ねが次の改善に弾みをつけ、継続的な改善活動につながっていくのです。
改善を「業務全体」で考える
「効果」と「実行しやすさ」という2つの軸で着手点を整理したら、次に重要になる視点は「業務全体を視野に入れる」ということです。
業務改善を進めるときに陥りがちなのが、個別の部署や担当者が部分的に改善を進めてしまうケースです。もちろん、現場ごとの効率化は大切ですが、部分最適にとどまると、「業務全体」として見た場合に非効率が残ってしまうことがあります。
たとえば、近年では経理部門が主導して、請求書発行をデジタル化しようとするケースがよく見られるようになりました。しかし、営業部門への共有やヒアリングが不十分だと、一部の取引先向けの請求書が新しいツールでは発行できないといった事態が起こります。経理の視点から見れば効率化を達成しているようでも、営業を含む会社全体ではかえって複雑化し、効率化どころか手間が増えてしまうこともあるのです。
改善の本質は、「全体最適」にあります。部署ごとに個別最適を追求するのではなく、前後の業務のつながりを意識して、全体を1つの流れとして見直すことが重要です。入力から承認、請求、入金といった一連のプロセスを俯瞰することで、本当に改善すべきポイントが見えてきます。
また、「属人化の解消」も業務全体を改善する上での大きなテーマです。たとえば、「Aさんしかシステムに入力できない」といった状況を放置すると、Aさんの休職や退職によって業務が滞るリスクがあります。業務を標準化し、誰でも同じ流れで進められるようにすることで、組織全体の安定性が高まります。
このように、業務改善では「目の前の便利さ」ではなく、「業務全体のつながりと持続性」を意識することが重要です。それによって、時間短縮やトラブル防止といった具体的な成果が表れてくるのです。
まとめ
業務改善に取り組もうとすると、多くの人が最初に直面するのが「どこから着手すべきか」という迷いです。思いつきや一部の声に引きずられて進めてしまうと、全体への効果が限定的になり、取り組みが空回りする恐れがあります。
大切なのは、効果が出やすく実行しやすい領域から、順序立てて取り組むことです。繰り返し作業が多く、時間のかかる業務や、売上や資金繰りに直結するプロセスは改善効果が目に見えて表れやすく、改善の第一歩に適しています。さらに、業務全体のつながりを意識して「標準化」や「属人化の解消」を進めることで、組織全体の安定性と持続性を高めることができます。
そして、忘れてはならないのが「小さな改善の積み重ね」です。わずかな改善であっても、それを継続し、成功体験として積み重ねていくことで、次の改善に弾みがつき、改善の文化を組織に根付かせることが可能になります。
ツールの導入はゴールではなく、手段です。いきなり新しい仕組みを取り入れるのではなく、まずは現在の業務全体を見渡し、課題を的確に捉えた上で初めの一歩を踏み出すことが重要です。