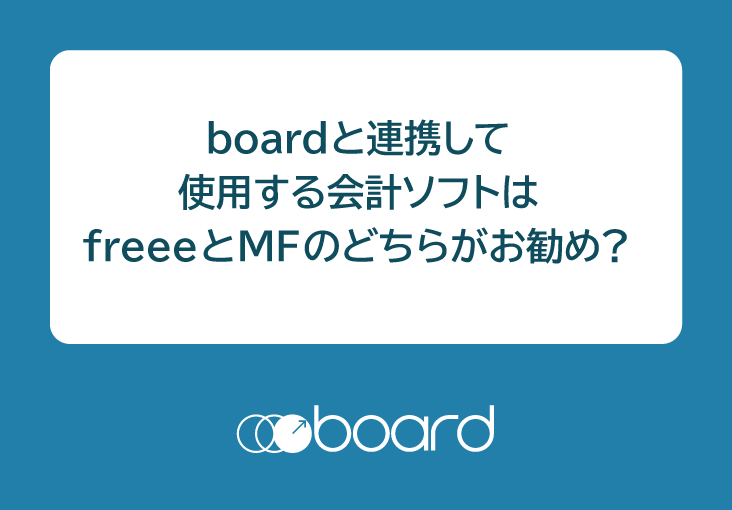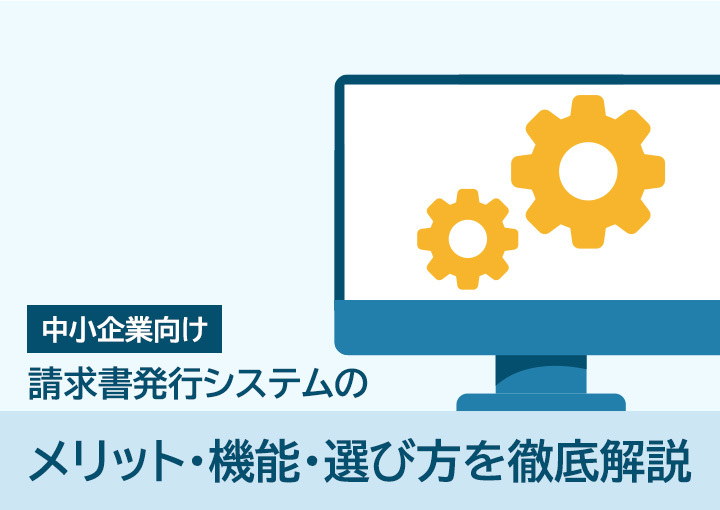プロジェクトごとの収支を管理したい、というニーズは中小企業でも多く見られます。とくに、外注費や仕入が発生する案件では、売上とコストを正しく紐付けて利益を把握しなければ、経営判断を誤るリスクがあります。
そこで重要なのが、「プロジェクト収支管理」です。ただし、中小企業では必ずしもプロジェクト管理ツールを導入する必要があるとは限りません。企業の規模やプロジェクトの性質によって、最適なやり方は異なります。
本記事では、プロジェクト収支管理の方法を「松竹梅」の3段階で整理します。高機能なプロジェクト管理ツールを活用する方法から、管理会計を用いる方法、販売管理ソフトをベースにしたシンプルな方法まで、自社の状況に合った管理方法を見つける参考にしてください。
税理士、業務設計士、リベロ・コンサルティング代表
金融のシステム企画部門、会計事務所、数社のスタートアップのバックオフィスを経て、独立。
既存の業務やシステムの使用方法を徹底的にヒアリングしながら、最適な業務フローとシステムの構成を設計し、業務からシステムまで再構築の実績多数。
業務設計の支援を手がけるリベロ・コンサルティング代表をメインで活動中。
プロジェクト収支管理が必要になる場面
「プロジェクト」とは、一定の目的や納期があり、複数の人や外部パートナーが関わって進める仕事のまとまりを指します。文脈によって、いわゆる「案件」を指すこともあれば、複数の案件のまとまりを指すこともあります。本記事では、そのどちらも含む汎用的な概念として扱います。
プロジェクト型の仕事は、中小企業でも日常的に発生します。たとえば、イベントの開催、新製品の開発、システム導入などです。そうした場面では、プロジェクト単位で状況を把握することが求められます。
とくに期間が長いプロジェクトになると、請求や支払いが複数回に分かれたり、着手金などの前受けや前払いの処理が必要になるケースも出てきます。そうしたプロジェクトが同時に進む場合は、何らかの方法でプロジェクト管理を行う必要が生じます。
プロジェクト管理においては、進捗状況やリソース管理ももちろん重要ですが、どの案件が利益を生んでいるのか、どの案件が赤字を出しているのかという経営の視点から状況を把握することが欠かせません。そのためには、売上や経費を案件ごとにまとめて見る仕組みが必要になります。
では、どうやってプロジェクトの収支を管理すればいいのでしょうか。世の中には多くのプロジェクト管理ツールがありますが、それらを導入しさえすれば、簡単に管理ができるというわけではありません。企業の規模や状況によっては、ツールの導入が必須でない場合もあります。「プロジェクト管理をしなければいけないから、プロジェクト管理ツールを導入しよう」と短絡的に決める前に、どのようなやり方があるのかを具体的に整理してみましょう。
プロジェクト収支管理の松竹梅
一口にプロジェクトの収支管理と言っても、その方法は企業の規模やプロジェクトの特性によって大きく異なります。ここでは「松」「竹」「梅」の3つのレベルに分けて整理します。
松:プロジェクト管理ツールを導入する
大規模な企業や案件数が多い企業に適した方法です。1年以上にわたるプロジェクトや10人以上が関わる案件が常に複数走っている場合、表計算ソフトでは管理が追いつかなくなります。専任の管理担当者を置き、プロジェクト管理ツールを導入することで、進捗・工数・収支を一元的に把握できます。ただし、初期設定や運用には一定のリソースが必要になるため、中小企業では導入が難しくなるケースもあります。
竹:管理会計をベースにする
数ヶ月から半年程度のプロジェクトで、3〜5人程度が関わる案件を管理するのに向いています。外注費や人件費をプロジェクトコードで紐付け、会計ソフトや表計算ソフトを活用して管理するスタイルです。人件費や外注費を稼働実績に基づいて按分できるため、精度の高い収支把握が可能です。ただし、会計ソフトで行う際は上位プランが必要になることが多く、その追加コストと、会計ソフトの中で処理が完結するメリットを比較して判断する必要があります。利用シーンとしては、少数精鋭で複数の案件を並行して回すような場合に適しています。
梅:販売管理ツールで案件収支を見る
最もシンプルな方法です。数人規模のプロジェクトで、粗利レベルの管理を目的とする場合に適しています。売上に対応する仕入や外注費を紐付けることで、案件ごとの収支を把握できます。この方法では、基本的には人件費や細かい費用の按分まではできませんが、案件単位の損益をつかむには十分です。一般的な方法としても活用できますし、さらにboardを利用すれば「案件」を単位に請求と支払を管理できるため、分割請求や複数回の仕入にも対応しながら、プロジェクト収支を把握できます。
| レベル | 適した規模・状況 | 使用するツール | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 松 | 大規模企業、10人以上で1年以上のプロジェクトが複数 | プロジェクト管理ツール | 進捗・工数・収支を一元的に把握しやすい | 導入・運用コストが高い、中小企業には過剰 |
| 竹 | 中規模、数か月〜半年、3〜5人規模 | 会計ソフト+表計算ソフト | 人件費や外注費を按分し、精度の高い収支把握がしやすい | 会計ソフト上位プランが必要になる場合あり |
| 梅 | 小規模、数人規模の案件、粗利管理が中心 | 販売管理ツール | 案件ごとの収支を簡単に把握しやすい、boardで対応可 | 人件費の按分は不可、詳細な管理は難しい |
どの方法にも一長一短があります。重要なのは、自社の規模やプロジェクトの特性に合ったやり方を選ぶことです。まずは、自分たちがどのレベルの管理を必要としているのかを明確にし、その上で適切なツールや仕組みを導入する。それが無理なくプロジェクト収支を管理するための第一歩になります。
まとめ
プロジェクトの収支管理は、中小企業にとっても重要なテーマです。ただし、そのやり方は一様ではありません。企業の規模やプロジェクトの性質によって、必要とされる管理レベルは大きく異なります。
「松竹梅」で整理したように、専用のプロジェクト管理ツールを導入して細部まで管理する方法もあれば、管理会計を軸に収支を把握する方法、販売管理ツールを活用して案件ごとの粗利をつかむ方法もあります。それぞれにメリットとデメリットがあり、どれが正解というものではありません。一般的には、中小企業で人件費や費用を按分して管理する必要があるケースは多くないと考えられます。
プロジェクト管理ツールは確かに高機能ですが、中小企業にとっては、その導入コストや社内の対応リソースは相当に重く、導入後も相応のメンテナンスコストとリソースが必要になります。プロジェクトの収支管理をしたいという段階であれば、まずは販売管理ツールを活用して、粗利レベルで管理するところから始めるのが現実的です。
会計ソフトを使って管理会計の仕組みを強化するやり方も、日々の会計処理で正確にプロジェクトを把握し、期間費用を適切な基準で按分するなど、きちんとした経理体制が前提になります。
その点、販売管理ツールのboardは、「案件」単位での収支管理がすぐにできる構造になっています。中小企業でも導入時の追加のリソースやメンテナンスコストは不要で、案件の収支をわかりやすく把握できます。
大切なのは、自社がどの程度の管理を求めているのかを明確にすることです。それによって、自社に合った方法の選択や、継続的に収支を追える仕組みを持つことが可能になり、健全な経営判断につながっていくのです。