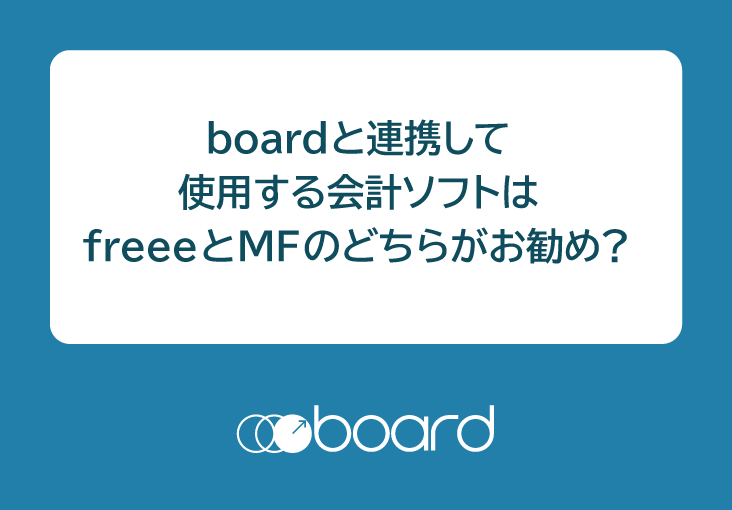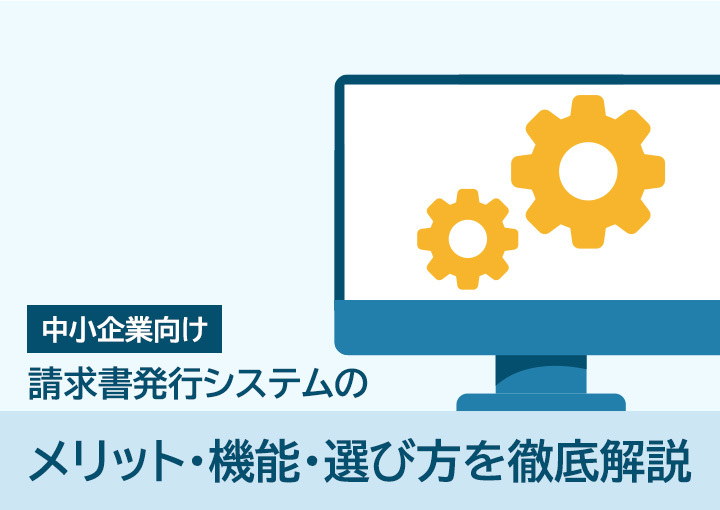近年、あらゆる業種でSaaSの導入が加速しています。SaaS(Software as a Service)とは、インターネットを通じて提供されるクラウド型のソフトウェアです。営業管理や会計処理、在庫管理や人事労務まで、SaaSを活用すれば中小企業でも高度なシステムを使えるようになりました。導入のハードルは格段に下がり、以前のように数千万円規模のシステム投資を覚悟する必要もありません。
一方で、「SaaSを導入したのに、思ったほど成果が出ない」という声も少なくありません。その背景には、共通するアンチパターン(よくある失敗のパターン)があります。とくに多いのが「自社の業務を整理せず、今の業務に合ったSaaSを探す」というケースです。今ある業務のやり方をそのまま固定してしまうと、それにピッタリ合うSaaSに出会うことは難しく、いつまでも探し続けることになりがちです。
確かに、自社に適したSaaSを選ぶことは大切です。ただし、「現在の業務を一切変えない」ことを前提にした探し方では、最適解にたどり着くことはほぼ不可能です。むしろSaaS選びが迷走し、導入後も「やっぱり使いにくい」と不満が残りやすくなります。
本記事では、このアンチパターンがどのような経緯で生まれるのか、そして成功させるためには何から始めるべきなのかを解説していきます。
税理士、業務設計士、リベロ・コンサルティング代表
金融のシステム企画部門、会計事務所、数社のスタートアップのバックオフィスを経て、独立。
既存の業務やシステムの使用方法を徹底的にヒアリングしながら、最適な業務フローとシステムの構成を設計し、業務からシステムまで再構築の実績多数。
業務設計の支援を手がけるリベロ・コンサルティング代表をメインで活動中。
「今の業務に合うSaaS探し」の落とし穴
SaaS導入に失敗する典型的な要因の1つが、「今の業務に合うSaaSを探す」という発想です。現状の業務プロセスはそのまま維持して、それにフィットするサービスを探し回るというやり方は、一見合理的に見えますが、そこに落とし穴があります。
そもそもSaaSは、幅広い企業で共通するニーズを満たすように設計されています。そうすることで、高度な機能をリーズナブルな価格で提供できる仕組みになっているのです。もちろん、業種や業態に応じた要件に対応するために一定の柔軟性は持たせてありますが、従来のやり方と完全に一致するサービスは存在しないと考えるべきです。「うちの業務に100%フィットするサービスがあるはずだ」と考えはじめると、選定のプロセスは長引き、導入が遅れるだけでなく、最終的に「どれを選んでもしっくりこない」という結果を招きかねません。
さらに厄介なのは、この探し方をしてしまうと、「業務をもっと効率化できるように見直す」という意識を持てなくなるということです。SaaSの導入では、そのサービスの標準的なプロセスに寄せていくことで、効率化や生産性向上の効果を発揮しやすくなります。業務を見直さないままでは、せっかくの機能も十分に活かせず、結果として「導入したのに結局使っていない」「一部の部署しか活用できない」といった事態に陥りやすくなります。
つまり、SaaS導入の第一歩は「今の業務に合うサービス探し」ではありません。「現在の業務に無駄や重複がないか」「属人化していないか」といった視点で自社の業務を整理することが出発点になるのです。
カスタマイズに頼りすぎる危険性
「自社の業務に合わないなら、カスタマイズすればいい」と考える企業も少なくありません。とくにSalesforceのように、高度なカスタマイズ性を持つSaaSであれば、カスタマイズをすればするほど理想の業務フローに近付けると思えるかもしれません。
しかし、過剰なカスタマイズには大きなリスクがあります。第一に、SaaSの本来の魅力である「継続的なアップデート」の恩恵を受けにくくなることです。独自のカスタマイズが多いほど、SaaS開発企業が提供する新機能や改善された機能を利用できなくなったり、システムが複雑化してしまったりする可能性が高まります。
第二に、メンテナンスの負担が重くなるという問題があります。大企業であれば、専任のエンジニアを配置して対応し続けられるかもしれませんが、中小企業では現実的に難しいことが多いでしょう。独自のカスタマイズは、それを維持するために相当のコストとリソースを必要とします。さらに担当者が異動や退職をすれば、システムがブラックボックス化してしまう危険性も高まります。
SaaSは「標準機能を活用すること」でこそ力を発揮します。カスタマイズは最小限にとどめ、自社の業務をできるだけ標準機能に寄せていく方が、長期的に見てコストも手間も抑えられ、結果として業務改善の効果を持続させやすいのです。
SaaSの本来の価値
SaaSがこれほど広く普及した背景には、オンプレミス型にはない明確なメリットがあります。その代表が「サブスクリプションモデルによるコストの見積もりやすさ」と「継続的な機能アップデート」です。
オンプレミス型のシステム導入では、初期投資として数百万円から数千万円規模の費用を要し、その後もバージョンアップや保守契約で追加の支出が発生するのが一般的でした。これに対して、SaaSは月額や年額の利用料を支払うだけで、常に最新機能を利用できる仕組みです。企業はSaaSの登場により、中長期的なコストを予測しやすく、限られた予算の中でも高度なシステムを活用できるようになったのです。
また、SaaSのメリットとしてとりわけ重要なのが「継続的なアップデート」です。SaaSの開発企業は、ユーザーからの要望や市場環境の変化に応じて、機能改善や新機能の追加を行い続けます。ユーザーは追加費用を払わずとも、その恩恵を受けられます。標準機能を活用する限り、こうした改善は自動的に反映され、常に最新の環境で業務を進められます。
このように、SaaSの価値は「安定的に予算を組めること」と「進化し続ける仕組みを享受できること」にあります。こうしたメリットを活かすためには、過剰なカスタマイズを避けることが重要です。
業務の整理と再設計の重要性
SaaSの導入を成功させるために欠かせないのは、「業務の整理と再設計」です。「SaaSを導入すれば自動的に効率化できる」と考えてしまうと、アンチパターンにはまってしまいます。業務そのものが複雑で、無駄が多いままでは、どんなに優れたツールを導入しても効果は限定的なのです。
まず取り組むべきは、現状の業務プロセスを丁寧に洗い出すことです。「この作業は本当に必要か」「二重入力や重複作業になっていないか」「属人化していないか」といった観点で見直していくと、改善の余地は少なからず見つかります。単に効率化を目的とするのではなく、全体の流れを整理し、業務の負荷やリスクの低減を意識することが大切です。
このプロセスを経ることで、初めて「業務をより効率化するためのSaaS」を選ぶことができます。業務を整理する中で、SaaSの機能に対する要件も明確になり、本当に自社に合ったSaaSが見えてくるからです。多くの企業が理想を求めすぎるあまり迷走しがちですが、検討にあたっては、まず何よりも「完璧なSaaSというものは存在しない」と理解しておく必要があります。
自社に合ったSaaSであれば、標準機能だけで十分に活用できます。業務をシンプルに再設計することで、SaaSの機能と自然に噛み合い、導入効果を最大化することができます。SaaSの機能と業務の再設計という両輪が揃うことで、業務は初めて効率化されるのです。
構築した当時は最適だった業務プロセスも、時間の経過とともに少しずつ非効率になっていきます。しかし多くの場合、そのような問題は見直されずに蓄積されていきます。新しいSaaSの導入は、自社の業務をあらためて点検する良い機会なのです。
まとめ
ここまで見てきたように、SaaS導入におけるアンチパターンの中でもとくに多いのが「今の業務に合うSaaSを探し求める」「過剰にカスタマイズしてしまう」の2つです。このようなアプローチは、せっかくのSaaSの魅力を活かせず、結果的に使われなくなってしまう要因になりかねません。
SaaSが本来持つ価値は、サブスクリプションモデルによるコストの予測しやすさと、継続的に進化していく仕組みにあります。そのメリットを最大限に享受するには、標準機能をベースに活用することが不可欠です。
だからこそ重要なのが「業務の整理と再設計」です。業務の無駄や属人化を見直し、シンプルに組み立て直すことで、SaaSを選ぶ際の要件も見えてきます。自社に合ったSaaSを選んだ結果、導入効果が持続し、組織全体で業務改善のサイクルを回せるようになります。
SaaSは魔法の杖ではありません。しかし、業務の改善とセットで導入を進めれば、強力な味方になります。導入にあたっては、SaaSを「自社の業務をアップデートするための道具」として位置づけることが重要です。