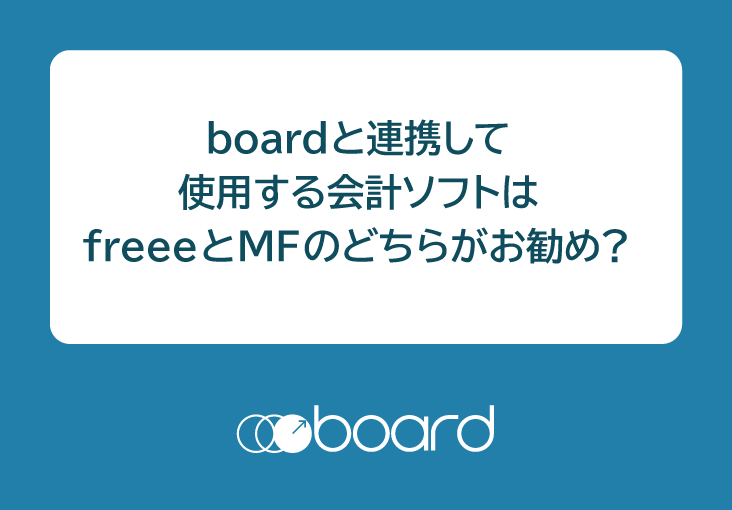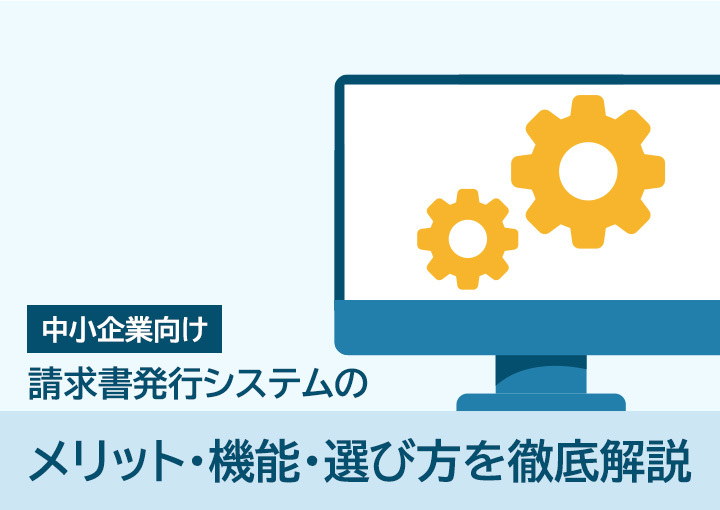経理にとって、「売上計上」は日常業務の中でもとくに基本的な処理の1つです。月次の締め処理において、売上が正しく計上されているかを確認することは、財務会計の正確性に直結します。長年経理業務を担当されている方であれば、「まずは売上の数値を固める」というやり方が定着していることでしょう。
しかし、boardにはそのような意味での「売上計上」という考え方は存在しません。たとえば、案件の受注ステータスが「受注確定」や「受注済」になると、ダッシュボードではその案件の金額が売上として認識されます。つまり、boardでは請求書発行やサービス提供といったタイミングに基づいて売上が計上される仕組みにはなっていません。
boardは販売管理ソフトであり、将来の売上や仕入、利益の見通しを立てることに重きを置いています。経営判断や進捗管理に役立つ情報を重視した設計で、「今、どの案件が、どのフェーズにあり、どのタイミングで請求が発生し、利益が見込めるのか」を可視化することがboardの役割なのです。
この記事では、こうしたboardでの数字の見方について、財務会計との違いを軸に整理していきます。経理にとっての「当たり前」と、boardの世界観がどう違うのか。その違いを理解することで、boardをよりスムーズに活用できるようになるはずです。
税理士、業務設計士、リベロ・コンサルティング代表
金融のシステム企画部門、会計事務所、数社のスタートアップのバックオフィスを経て、独立。
既存の業務やシステムの使用方法を徹底的にヒアリングしながら、最適な業務フローとシステムの構成を設計し、業務からシステムまで再構築の実績多数。
業務設計の支援を手がけるリベロ・コンサルティング代表をメインで活動中。
会計上の「売上」とは
会計における「売上」は、企業が商品やサービスを顧客に提供し、その対価として金銭を受け取る権利が確定した時点で認識されます。つまり、単に請求書を発行したかどうかではなく、実際にモノやサービスを提供したかどうか、そしてその対価を受け取る権利が確定しているかという実質に基づいて判断するのが会計的な考え方です。
とはいえ、中小企業の経理において、ここまで厳密な定義を考えながら売上計上の処理をしているケースはほとんどありません。基本的には、中小企業では「請求書の発行=売上計上」であり、発行済みの請求書を元に経理で処理をしているのが大半です。つまり、請求書が発行されたものは「売上が確定したもの」として扱われます。
一方で、boardのような販売管理ソフトには、このような売上計上の概念はありません。なぜなら、boardは「売上の確定」ではなく、「見込みと実現の管理」に重点を置いているためです。
boardで扱う「売上」は、案件の進捗を元に将来の見通しを管理するためのもので、会計上の「売上」とは考え方が異なります。
この違いを知らないままboardを使おうとすると、「いつ売上が確定するのか?」「どの操作が売上計上にあたるのか?」といった戸惑いが生じるかもしれません。
board上の「売上」とは
boardでは、案件の受注ステータスを元に「売上」が認識されます。具体的には、「見積中」の段階では売上として扱われず、「受注確定」や「受注済」になったタイミングで、ダッシュボードの「売上サマリー」に反映されます。
ここで注意したいのは、board上で「売上」と表示される数値は、受注に基づいた見込みの金額であるという点です。この数値は、「今どれくらいの売上が見込まれているか」を把握するためのものであり、請求書の処理と直接の関係はありません。請求書はまだ発行されていないため、案件に紐付く請求書のステータスは「未請求」の状態です。
その後、納品が完了し、請求書が発行されて「請求済」となった段階で、会計上の売上が確定します。会計ソフトと連携している場合も、この「請求済」の段階で売上情報が連携される仕組みです。
「売上」のタイミングが異なる背景
このように、board上の「売上」と会計上の「売上」は、認識するタイミングが異なります。boardでは、経営管理の観点から「見込みの売上」を早期に把握することを重視しており、「受注確定」時点で売上として認識されます。一方で会計上の売上は、モノやサービスを提供し、その対価を受け取る権利が確定したタイミング、つまり「請求済」になったときに計上されます。
この違いによって、boardの管理上は売上が立っているように見えても、会計上はまだ売上として扱えないというズレが生じます。
たとえば、いったん受注が決まっても、その後キャンセルになったり、納品が遅れたりすると、請求書が発行できず、会計上の売上には反映されません。このように、見込みと実績の間にズレが生じることは実務上よくあります。
会計のルールでは、「対価を受け取る権利」が確定しなければ売上として認識できません。しかし、経営管理や営業の予実管理では、受注状況や納品スケジュール、請求予定などを元に、将来の売上の見込みを把握しながら行動計画を立てていきます。もし会計上の売上だけを基準にしてしまうと、現場の進捗が見えにくくなり、予算管理や目標の達成度を正しく把握できなくなってしまうのです。
経営・営業と経理の役割の違い
boardのダッシュボードは、経営陣や営業が利用するためのものです。請求書の発行を経理が担当している場合、営業は案件の受注ステータスを「受注確定」や「受注済」にするところまでが役割です。
経理側はダッシュボードの「今月未請求」の案件を確認し、そこから請求書を発行します。そして、発行された請求書が「請求済」となった時点で、会計上の売上が計上されることになります。
財務会計とboardの違い
経理の方にとって、「数字を見る」と言えば、まず思い浮かべるのは財務会計(会計ソフト)の数値でしょう。企業活動上で確定した情報を元に、会計基準などのルールに従って売上や費用を集計し、正しい損益を算出するのが財務会計の役割です。過去に確定した情報であるため、基本的には、経理が情報を認識した後に数字が変動することはありません。
一方、boardで扱う数字には見込み段階の金額も含まれているため、モノやサービスの提供状況や取引先とのやり取りによって、数字が変動する可能性があります。そのため、boardでは「案件」の受注ステータスと「請求書」の請求ステータスを別々に管理できるようになっています。
数字の役割の違い
財務会計とboardでは、「数字を見る目的」が異なります。財務会計は、過去の取引実績を整理し、法定帳簿や決算書として整えるために行われます。そのため、財務会計では制度上の正しさや網羅性が重要になります。一言でいえば、「制度に従って、確定した数字を記録する」ための仕組みと言えます。
対してboardは、実務や経営判断に役立てるための管理会計的な視点で構成されています。過去だけでなく、現在進行中の案件や将来の見通しも重要な管理対象です。つまり、boardでは「意思決定に使うための数字」を扱っていると言えます。
ある案件において「いくらで受注していて、どのタイミングで請求が発生するのか」といった情報は、会計ソフト上で表現することは難しいですが、board上では自然に管理できます。こうした情報は、たとえばキャッシュフローの予測や進捗確認など、現場でさまざまな判断をする際の材料になります。
「正確な情報を報告するための数字」と「意思決定に活かすための数字」。目的が違えば、使い方も変わります。どちらが正しいということではなく、それぞれの役割を理解し、適切に使い分けることが重要です。
| 財務会計(会計ソフト) | board | |
|---|---|---|
| 数字の目的 | 法定帳簿・決算書の作成 | 実務・経営判断に活用する |
| 時点 | 過去に確定した取引 | 現在〜将来の見通しを含む |
| 変動の有無 | 基本的に変動しない | 状況により変動する可能性あり |
| 情報の粒度 | 勘定科目・部門単位 | 案件・請求単位、担当者単位 |
| 管理の柔軟性 | 制度に準拠した固定的な構造 | 現場の実態に合わせた柔軟な構造 |
| 得られる示唆 | 財務的な結果の整理と報告 | キャッシュフローや進捗の把握・見込み管理 |
まとめ
経営や営業では、「今、動いている数字」が意思決定に使われます。一方で、経理が取り扱うのは「過去に確定した数字」です。
boardは、「今の数字」を把握するためのツールです。案件単位で進捗や見込みを管理することで、将来の売上やキャッシュフローを見通しやすくなります。これは、すでに確定した取引を記録する会計とは役割が異なります。
財務や税務のために正確な会計処理を行うことは、経理の基本的な仕事です。
しかし中小企業の経理には、それに加えて、案件の進捗を把握して請求や売上のタイミングを事前に確認したり、キャッシュフローの見通しを経営陣に伝えたりと、より経営に近い役割が求められることもあります。
財務会計とboardの違いを理解することは、経理の視野を広げ、経営判断に寄与する力を高めることにもつながります。管理会計や経営管理の視点を知ることで、財務会計の理解も深まります。経理としての視野を広げ、会社全体の動きと数字をつなぐ役割を果たすためにも、boardの性質を理解して、効果的に活用していきましょう。