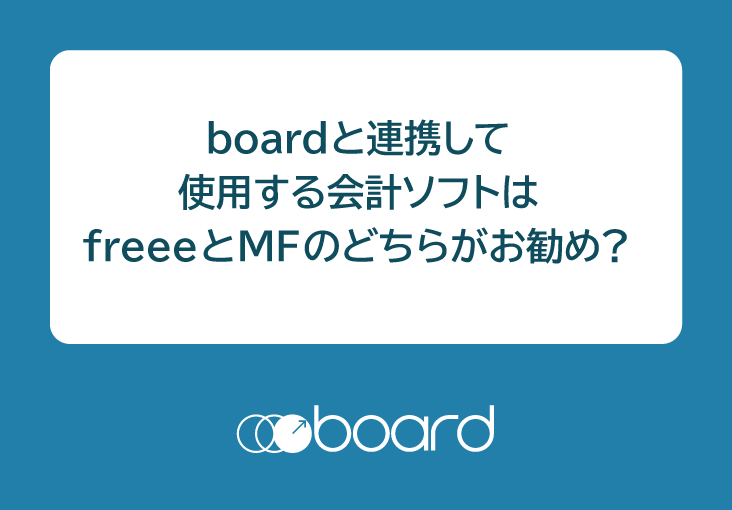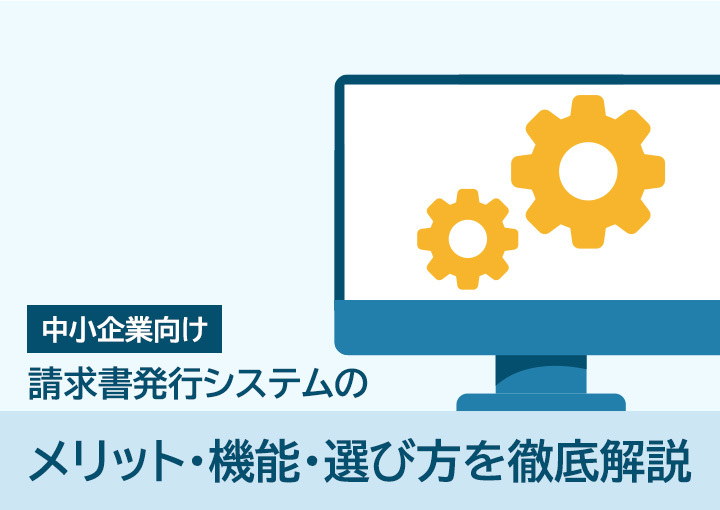請求書は、企業間取引や個人事業主の業務において欠かせない書類です。基本的な発行・受領の流れを理解することで、ミスの防止やスムーズな業務遂行につながります。
本記事では、請求書の発行側・受領側それぞれの基本的な流れと、実務上のポイントを分かりやすく解説します。
目次
請求書発行側の基本的な流れ
請求書を発行する側は、取引内容や契約条件に基づき、正確な情報を記載した請求書を作成し、相手先に送付します。以下は一般的な発行手順です。
1. 請求内容の確認
取引先との契約や注文内容、納品状況などをもとに、請求すべき金額や品目、数量などを正確に確認します。誤った請求は信頼低下や再発行の手間につながるため、事前のチェックが重要です。
2. 請求書の作成
インボイス制度に対応した適格請求書には、以下のような項目を記載します。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号(自社の会社名と登録番号)
- 取引年月日(請求日・納品日など)
- 取引内容(品目、数量、単価など)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 請求先(書類の交付を受ける事業者)の氏名または名称
近年はクラウド請求書サービスの利用が増えており、テンプレートや自動計算機能を活用することで、記載漏れや計算ミスを防げます。
参考:【中小企業・個人事業主向け】請求書作成・発行のキホン|業務効率化・ミス防止・法令対応など
3. 請求書の送付
作成した請求書は、取引先の希望や自社の運用に応じて、郵送・メール・クラウドサービス経由などで送付します。
昨今は、クラウド請求書サービス経由で送付することが主流になってきました。一括送付が可能なサービスも多く、送付業務の効率化に繋がるので、未導入の方は検討をお勧めします。
参考:月末月初に集中する請求書送付業務を効率化する方法|繁忙期を平準化してミスと残業を減らす
4. 入金確認
請求書送付後は、支払期日までに入金があるかを管理します。期日を過ぎても未入金の場合は取引先に確認を行います。
取引先社内のミスなどで振込処理が進んでいないケースなどもあるので、少なくとも月1回はチェックするようにしましょう。
クラウド請求書サービスを使うことで、未入金のものを確認しやすくなります。送付履歴とダウンロード有無の確認や入金状況の管理も容易になるため、業務効率化に役立ちます。
請求書受領側の基本的な流れ
請求書を受領する側は、受け取った請求書の内容を確認し、社内処理や支払い手続きを進めます。以下は一般的な受領手順です。
1. 請求書の受領・内容の確認
郵送・メール・クラウドサービスなどで請求書を受け取ったら、速やかに開封・確認しましょう。
請求内容が契約や納品状況と一致しているか、金額や品目に誤りがないかをチェックします。疑問点や不備があれば、速やかに発行元へ問い合わせましょう。
2. 担当部署への共有・支払い依頼
請求書の内容に問題がなければ、経理など支払い担当の部署へ請求書を共有します。
支払い担当の部署は、請求書を受け取ったら内容を確認し、必要に応じて承認を得るための手続きを行います。支払期限に遅れないよう、期日をしっかりと管理しましょう。
参考:受領した請求書を経理に共有し忘れたときの対処と再発防止策|受領後の抜け漏れを最小化する実務ポイント
3. 支払い手続き
承認後は、支払期日までに指定の振込先へ入金します。支払いが完了したら、支払記録を残し、請求書とともに保管します。
電子帳簿保存法への対応が必要な場合は、それに応じたデータ保存や証憑管理も忘れずに行いましょう。
まとめ|正しい流れの理解が業務効率化につながる
請求書の発行・受領は、企業活動の根幹を支える重要な業務です。正しい流れを理解し、ミスやトラブルを防ぐことで、信頼関係の構築や業務効率化につながります。
クラウドサービスの活用や社内ルールの整備も、今後ますます重要となるでしょう。