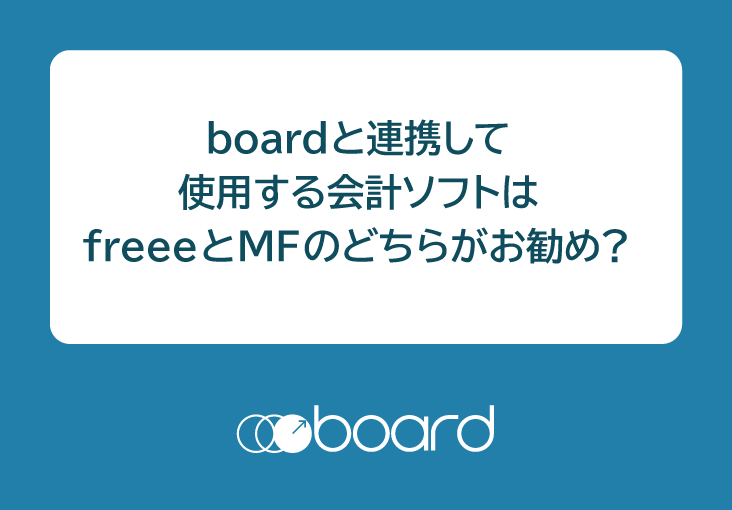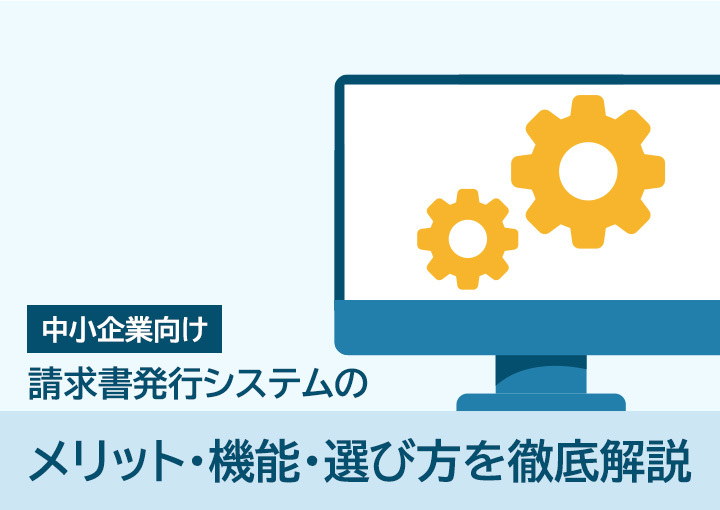請求書を発行するタイミングで直接会う機会があると、請求書を直接持っていき手渡しするということがあります。
メールの不達や郵便事故に巻き込まれずに確実に渡せるメリットがある一方、手渡し特有の課題も存在します。
この記事では、請求書を手渡しする際に起こりがちなトラブルや、より安全・確実に請求業務を進めるためのポイントを解説します。
目次
請求書を手渡しする場合の主なリスク
請求書の発行方法は、郵送やメール、クラウドサービス経由などさまざまな方法があります。その中でも「手渡し」は、相手に直接書類を渡せるというメリットがある一方で、以下のような課題が潜んでいます。
受け取った人から経理担当者への共有漏れ
手渡しの場合、請求書を受け取った担当者がそのまま机の上に置き忘れたり、経理担当者へ渡し忘れるケースが少なからずあります。とくに営業担当や現場担当が受け取る場合、日常業務の中で請求書の共有が後回しになり、支払い処理が遅れる原因となります。
受け取る側からしても、普段行わないタスクだったり、直近でオフィスに立ち寄らない予定の場合は、直接経理に送ってほしいと思う可能性もあります。
「請求書は直接経理に送付した方が良いですか、それとも手渡しでも良いですか」という確認をするのも良いでしょう。
渡したことの記録が残らない
手渡しの場合、「いつ・誰に・どの請求書を渡したか」という履歴が残りません。そのため、未入金が発生した場合に、請求書を発行済みなのか確認が難しくなってしまいます。
- 「請求書を受け取っていない」「渡した・渡していない」の水掛け論になる
- 支払い遅延や未払いの原因が特定できず、責任の所在が曖昧になる
一方、メールで請求書を送付した場合は送信履歴が残り、クラウド請求書サービスを利用すれば「ダウンロードしたか」まで記録されます。これにより、トラブル発生時も履歴を確認して迅速に対応できます。
請求管理を行っている一覧への反映漏れ
手渡しで請求書をやり取りすると、請求管理システムや一覧表への反映が漏れるリスクがあります。
事前にステータスを変更してしまうと渡し忘れた場合に不整合な状態になってしまいます。一方、手渡しして帰社後に反映しようとすると、うっかり忘れてしまうこともあります。
システム外でのやり取りが増えると、データの整合性が保てなくなる要因が増えるため、注意が必要です。
手渡し以外の方法を活用するメリット
請求書のやり取りは、できるだけ履歴が残る方法を選ぶのが安全です。とくに以下のような方法は、手渡しに比べて多くのメリットがあります。
メール送付
- 送信履歴が残るため、トラブル時の証拠になる
- 複数の担当者に同時送信でき、共有漏れを防げる
- PDF化により、原本紛失リスクも低減
クラウド請求書サービスの利用
- 送付・受領履歴が自動で記録される
- ダウンロード状況や開封確認も可能
- 請求管理システムと連携しやすく、一覧への反映漏れを防げる
発行手段を絞ることによる効率化
請求書の発行手段が多岐にわたると、管理が煩雑になり、ミスや漏れの原因となります。可能な限り発行手段を絞り込み標準化することで、業務効率化とリスク低減が図れます。
これについては「顧客ごとに送付方法(メール・郵送・専用アップロード等)が異なる請求書の効果的な管理方法」に詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
まとめ|請求書の手渡しは最小限に、履歴と管理を重視しよう
請求書の手渡しは、相手に直接渡せるという安心感がある一方で、履歴が残らずトラブルの温床にもなりやすい方法です。
経理担当者への共有漏れや請求管理一覧への反映漏れなど、実務上のリスクを十分に理解し、できるだけメールやクラウドサービスなど履歴が残る方法を推奨します。
システム外のやり取りが増えると、データの整合性が保てなくなる要因が増えるため、注意が必要です。
請求書発行システムのような仕組みを使っている場合、すべてのデータがそこに登録され、適切なステータスになっていることにより、状況の把握や後続業務へのスムーズな受け渡しが可能になります。そのため、安易にシステム外のことを増やすと、その価値が損なわれる可能性がありますので注意しましょう。