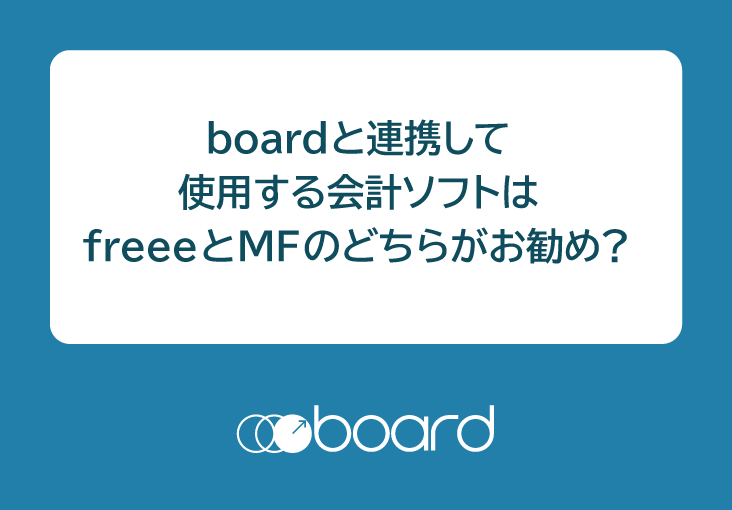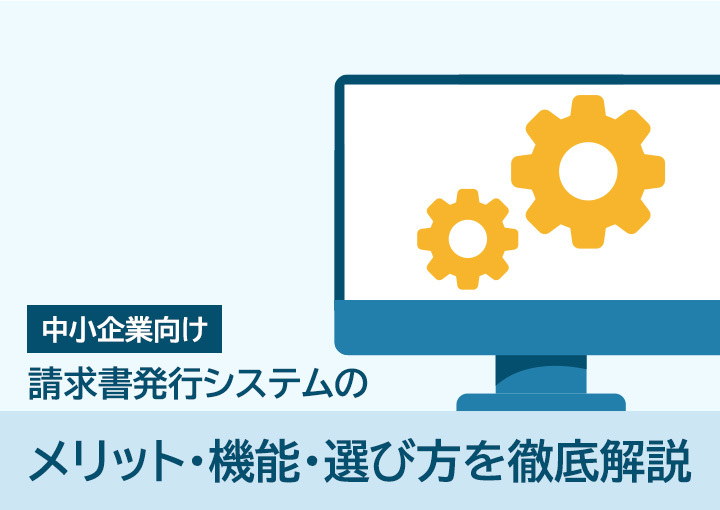請求書をメールで受け取ったとき、受領の返信をすべきか迷ったことはありませんか。送付側では「返信不要」と書くこともありますが、とくに記載がない場合はどう対応すべきか悩むことも多いでしょう。
本記事では、受領返信の必要性や判断基準など、受け取る側の視点でわかりやすく整理します。
受領返信は必須ではないが状況次第で使い分けましょう
受領返信の有無に正解はありません。重要なのは「状況と相手との関係性」を基準に判断することです。ここでは受領返信が不要とされる背景と、返信したほうが良い典型的なケースを整理します。
受領返信が不要とされる理由
受領連絡を省略する企業が増えている背景には次のような事情があります。
- 事務負荷の削減:月末や締め処理の時期に大量の請求書が届くと、個別に返信すると手間がかかるため。
- 処理フローの自動化:受け取った請求書を自動的にシステムに取り込むケースは人間が介在しないため。
- ニーズの少なさ:送付側がとくに受領確認を求めていない場合、返信すると逆に負担になることもあるため。
これらは特に取引量が多い企業や、継続取引が中心の業界で当てはまります。
また、受領請求書サービス宛に直接送付するケースが増えたことも、返信をしないことが受け入れられるようになってきた背景のように感じます。
たとえば、郵送で請求書を送付した場合、受領の連絡は行っていないことが多いように思います。それと同じと考えれば、メールでの請求書受領でも返信しなくても、とくに実務上は問題はないとも考えられます。
受領返信をしたほうが良い場面
受領返信を推奨する代表的な場面は次の通りです。
初回取引の場合
初回取引の場合は、受領メールを送ることで送付側に安心感を与えます。その際、「来月以降は問題がなければ返信しない旨」を添えると、双方にとって負担が少なくなります。
とくに、その会社の他の取引先が返信している場合には、「確認したら返信があるもの」という認識があるため、返信しないと不安に思われる可能性があります。
取引先から内容や受領の確認を求められている場合
先方からのメールで、明示的に内容や受領の確認を求められている場合は、依頼に従って返信するのが基本です。
返信不要の意思表示を受けたときの扱い
送付側が明示的に「返信不要」と書いている場合、原則は返信を省略して問題ありません。
ただし、確認事項や誤りがある場合は、速やかに返信して指摘することが重要です。
業界慣習や時代の変化とともに変わる対応
受領返信の慣習は業界や企業文化によって異なります。また、デジタル化や自動化の進展により、返信しないケースが増えてきているという流れもあります。
とくに、受領請求書サービス宛への送信が増えてきたあたりから、返信しないケースをよく見るようになりました。
このように、時代の変化に伴い、変わりうるものです。一旦、自社や自分の方針を決めた後も、適宜、状況に合わせて見直していくと良いでしょう。
まとめ
請求書の受領返信は一律の正解はなく、状況に合わせて、業務効率とリスク管理のバランスで判断することが重要です。
初回取引では受領返信が有用ですし、継続取引の場合は返信をしない方がお互いの負担が軽くなります。双方が気持ちよく運用できるよう、うまく意思疎通を図って省力化を図っていきましょう。
請求書を送る際のポイントは「請求書をメールで送ったのに返信がないときは?受領返信の有無と実務対応のポイント」にまとめていますので、あわせてご覧ください。