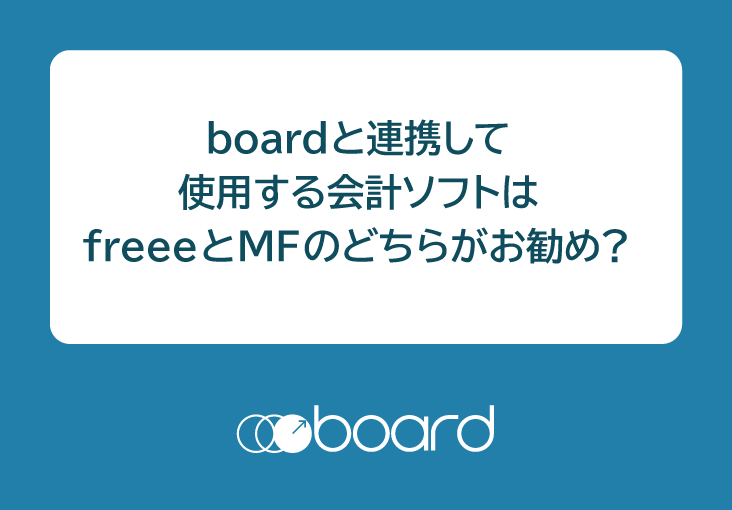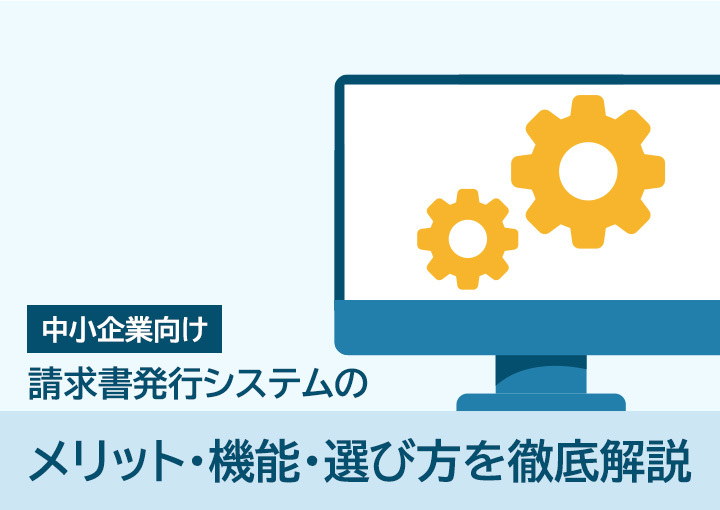請求書のやり取りにおいて、振込手数料を「どちらが負担するのか」は、意外と齟齬が発生するポイントです。
この記事では、振込手数料の基本ルールや業界・地域ごとの違い、トラブルを防ぐための明記方法まで、実務で役立つ知識を解説します。
目次
振込手数料の負担は原則「振込側」
請求書の振込手数料は、原則として振込を行う側(支払側)が負担します。
たとえば、10万円の請求に対して振込手数料が330円かかる場合、支払側は10万円+330円が引き落とされ、相手には10万円が振り込まれます。要するに、請求側は、請求した額面通りの金額を受け取るかたちになります。
このケースでは、請求側が本来受け取るべき金額を受け取ることができますので、一般的にはこのケースが多いと考えられます。
振込手数料を差し引いて振り込むケースも
一方で、業界や地域によっては「手数料を受取側が負担する」 というのが慣習になっている場合もあります。また、取引先との力関係も影響している可能性も考えられます。
この場合、支払側は請求金額の額面だけ引き落とされ、請求側は振込手数料を差し引いた金額を受け取ることになります。
具体的に「どの業界・地域」というほど明確には言えませんが、以前、あるお客さんが振込手数料を差し引いて振り込んでくるため、「契約書・請求書に書いてあるとおり、振込手数料はご負担ください」とお願いしたところ、「うちの地域だと普通は差し引いて振り込むので、経理はいつも通りに差し引いてしまっていた」ということがありました。
トラブルを防ぐために契約時・受注時に明確化を
上記のようなケースがあるようなので、振込手数料の負担については、契約書や発注書、見積書などで明確にしておくことが齟齬防止の第一歩です。特に、初めての取引先とのやり取りでは、事前の確認が欠かせません。
明記例
- 契約書に「振込手数料は甲の負担とする」などと明記
- 見積書・発注書・請求書の備考欄に「振込手数料は貴社ご負担でお願いします」「振込手数料は当社が負担します」などと記載
とくに契約時・受注時に明確にしておくことで、後々の誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。
boardでは、顧客ごとに「振込手数料負担」を「先方」か「当方」か選択できるようになっています。顧客ごとの振込手数料の負担が明確になるだけでなく、請求書の備考欄に「*お振込手数料はご負担願います。」と自動で記載されます。これにより、請求書を受け取った側も振込手数料の負担が明確になるため、先方のミスも防止できます。
よくある質問(FAQ)
Q. 振込手数料は振込側負担のはずだったのに手数料が差し引かれて振り込まれました。どうすれば良いですか?
まずは、契約書や請求書などを確認し、振込側が負担することになっていたかどうかを念のため確認しましょう。
振込側が負担することが明記されていたにもかかわらず差し引かれて振り込まれた場合は先方にその旨を連絡します。
その後の対応方法についてはいくつかの選択肢が考えられます。
- 継続取引の場合は、次回の請求書で差し引かれた分を上乗せして請求する
- 今回に限り、差し引かれた分は請求しない
- 差し引かれた分のみを請求する
振込手数料は少額ですので、それだけを追加請求することは躊躇われることも多いのではないでしょうか。そのため、上記の1つ目または2つ目の選択肢を選ぶことが多いようです。
迷う場合は会社の顧問税理士に相談しましょう。
まとめ
請求書の振込手数料は、原則として振込側(支払側)が負担しますが、業界や地域によっては異なる慣習が存在する可能性があります。トラブルを防ぐためには、契約時や受注時に「どちらが負担するか」を明確にし、請求書にもその旨を記載しておくことが大切です。
明確なルールと丁寧なコミュニケーションで、スムーズな取引と信頼関係の構築を目指しましょう。