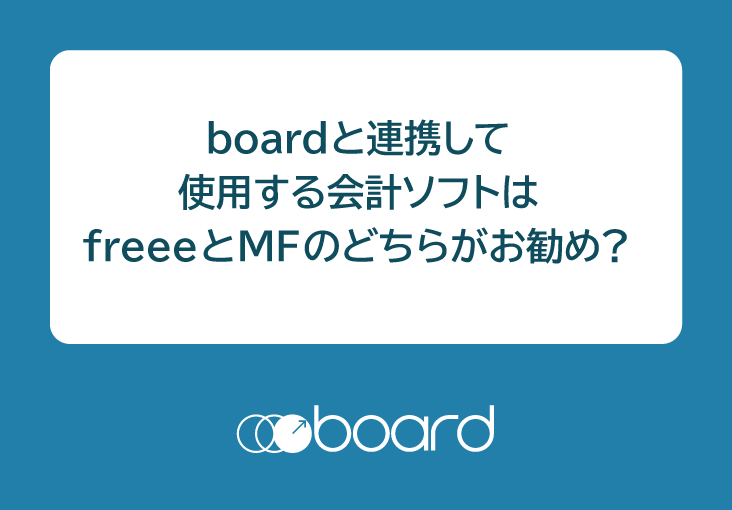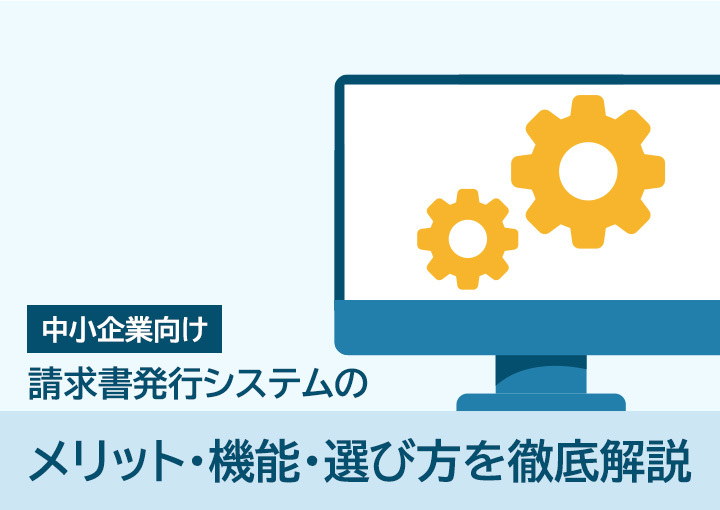複数案件が同時進行している場合、「案件ごとに請求書を分けるべきか」それとも「合計請求書としてまとめるべきか」という判断は、多くの事業者が迷うポイントです。
本記事では、請求書の分け方・まとめ方の基本的な考え方と、実務での使い分けのコツを解説します。
目次
複数案件の請求書は分けるのが基本
複数の案件を並行して進めている場合、以下のような理由で、案件ごとに請求書を分けるのが基本です。
案件ごとの請求金額が明確になる
案件を分けて請求することで、契約と請求が対になることになりますので、自社にとっても取引先にとっても、それぞれの取引の金額がはっきりし、後日の確認や会計処理が容易になります。
とくに案件(受注)単位で仕事をしていくタイプのビジネスモデルの場合は、案件ごとに請求を管理する方が適切に状況を把握できるはずです。
顧客側の部署ごとの処理に対応しやすい
顧客によっては、案件ごとに担当部署や担当者が異なります。請求書を案件別に分けることで、相手先の社内処理がスムーズになり、入金遅延のリスク軽減にもつながります。
合計請求書が適するケース
一方で、案件をまとめて1枚の請求書として発行する方が適しているケースもあります。
顧客の要望でまとめる場合
顧客が「請求はまとめてほしい」と希望するケースでは、複数案件を合計して1枚にします。このように、顧客が「こういったかたちで請求書を作成してほしい」という要望があるケースがありますので、まずは顧客の意向を確認することが重要です。
社内管理上分けている案件を外部向けにまとめる場合
自社の業務上、1案件を複数に分割して管理していても、顧客から見れば単一案件の場合があります。その場合は、顧客にとってわかりやすい形で合算して請求するのが適切です。
「月締め」ビジネスモデルにおける請求書
月内に複数回受注がある業態では、都度請求ではなく月末締めで1枚の請求書を発行することが一般的です。これは厳密には案件の合計というよりも、期間ごとにまとめる請求書の形です。
たとえば卸売や定期納品型の取引では、日々の受注や納品が個別に発生しますが、月末にまとめて請求します。この場合、受注単位ではなく期間単位での合算となるため、「合計請求書」に近い性質を持ちます。
この場合は、「合計請求書」の本来の意味とは異なるため、業務担当者からすると「合計請求書を作成している」という感覚は薄いかもしれません。一方で、クラウド請求書サービスを利用している場合は、「合計請求書」機能を活用する可能性があるため、認識とのギャップがある可能性はあります。
このように「合計請求書」「請求書を1つにまとめる」という言葉の意味は、文脈によって異なる場合があるため、注意が必要です。
まとめ
このように、請求書を個別に分けるか、合計請求書にまとめるかは、以下のポイントを考慮して判断します。
- 複数案件の場合は、案件ごとに請求書を分けるのが基本
- 顧客の要望や案件の性質によっては合計請求書を発行することもある
- 月締め取引では期間単位の請求書が主流で、合計請求書に近い形態になる
請求書の分け方・まとめ方は自社・顧客の管理性や請求書の意味付けなどを考慮して選ぶことが重要です。状況に応じて柔軟に使い分けることで、取引の円滑化とトラブル防止につながります。