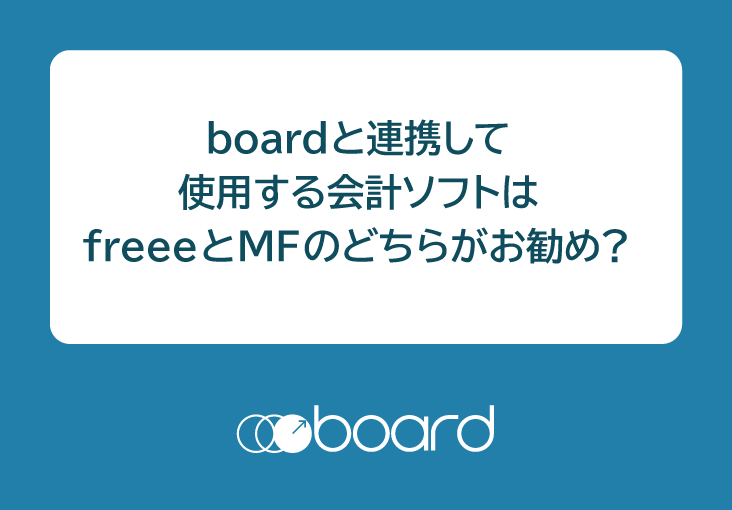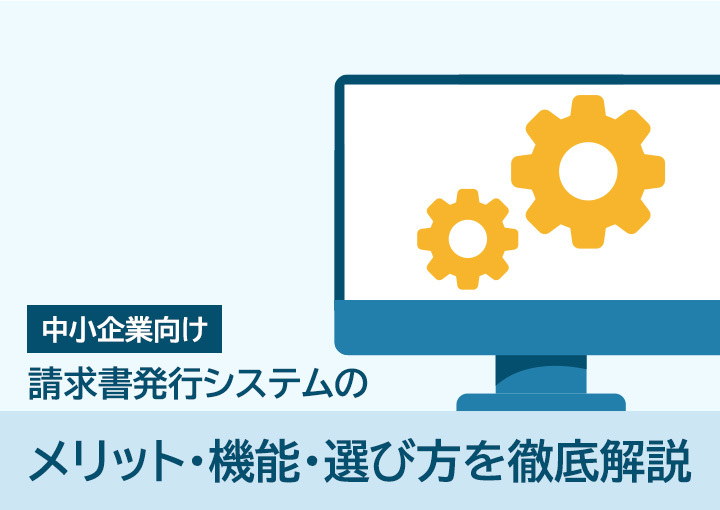請求書の送付漏れは、売上の遅延や未入金、取引先との信頼低下といった実務上の問題を生みます。豊富な取引や多拠点運用、手作業の多いワークフローほど漏れが発生しやすく、早めの仕組み化が重要です。
本記事では、クラウド請求書サービスを軸に、受注から請求までのデータの流れ作り、請求書発行担当者への情報共有の仕組み化、送付操作と連動したステータス管理、未請求のアラート設定など、現場で使える具体的な対策を紹介します。
目次
受注から請求までのデータの流れを作る
請求漏れの多くは「情報が個人の頭の中」や「複数システム間で同期されていない状態」から生じます。まずは受注→納品→請求というデータの流れを明確にして、自動的に次工程へ情報が渡る仕組みを作りましょう。
受注データの一元化
受注をメールや紙、複数のツールで管理していると抜けが発生します。受注に至るまでの経路は様々であっても、最終的には一つのシステムに受注情報を集約しましょう。
納品完了をトリガーに請求準備
納品が完了したという事実を請求の起点にします。納品確認が手作業の場合は、納品担当が請求処理のために「請求して良い」フラグをワンクリックで立てられるようにすると運用が簡素化されます。
受注・納品・請求のデータ連携
受注、納品、請求の各データを連携させることで、情報の抜け漏れを防ぎます。具体的には以下のような方法が考えられます。
- 見積もり・受注・納品・請求を一貫して管理できる販売管理ソフトを導入
- 各業務が別々のシステムの場合は、APIによる自動連携や、CSVによるデータの受け渡し
boardでは、受注・納品・請求を一元管理できるため、各データの連携が自動的に行われ、情報の抜け漏れを防ぎます。この一連の流れがよく設計されているのがboardの強みです。
参考:クラウド請求書サービスが他のサービス・システムと連携できるメリット
送付操作と連動したステータス管理
請求書の送付操作(PDF発行、メール送信、郵送指示など)に合わせてステータスを自動変更し、誰がどの段階にあるか一目で分かるようにします。
ステータスは送付操作に紐づけて自動更新することが理想です。システム内で「メール送信」操作を実行すると、該当請求書のステータスが自動で「請求済み」に変わることで、「ステータスの変更漏れ」を防げます。
たまに、クラウド請求書サービスでPDFだけ作成し、それをダウンロードして自分のメールから送信しているケースを見かけますが、これでは送付とステータスが連動せずミスの温床になります。クラウド請求書サービスのメリットを活かせないため、注意しましょう。
boardでは、請求書の送付(メール・郵送)操作に連動してステータスが自動更新されます。これにより、送付漏れやステータスの変更忘れを防ぎ、請求業務の正確性と効率性を向上させます。
未請求のアラートを仕組み化する
未請求のアラートは請求漏れ防止の重要な手段です。自動通知があれば、人手に頼らずに未処理を早期に発見できます。
アラート設計のポイント
アラートは「いつ」飛ばすかを検討します。たとえば以下のような設計が考えられます。
- 請求日の3営業日前に通知(事前に請求準備を促す)
- 請求日の当日に通知(当日のTODOとして認識させる)
- 請求日の翌営業日に通知(請求漏れを早期発見)
boardの「通知機能」では、複数回、営業日に基づいた通知設定が可能です。上記のような設定をすることで、スムーズな請求業務と漏れ防止に役立ちます。
ダッシュボードと定期レポート
クラウド請求書サービスのダッシュボード(ログイン直後に表示される画面)に未請求の件数やリストが表示されていると、日々に業務の際に確認できます。アラートと併用して、日常的にダッシュボードを確認するようにしておくと良いでしょう。
実務上の注意点と落とし穴
仕組み化でカバーできる範囲は広いですが、運用上の注意点もあります。
人的ミスを完全になくすことはできない
仕組みは人的ミスを減らすが、完全にゼロにすることは困難です。定期的なチェックや、月次で未請求の確認を実施することを推奨します。
システム依存リスク
クラウド請求書サービス上で管理することで、ミスを大幅に減らすことができますが、そもそもシステムに登録し忘れてしまっては、その仕組みが意味をなしません。最初に「データを登録する」という業務や受注ステータスを変更することなど、データ信頼性に関わる抜け漏れが起きないように注意しましょう。
まとめ
請求書の送付漏れは、仕組み化により大きく削減できます。受注から請求までのデータの流れを作り、送付操作と連動したステータス管理や未請求アラートで見逃しを防ぎましょう。
クラウド請求書サービスを選定する際は、請求書の作成部分だけでなく、受注・納品から請求までの一連の流れをカバーできるか、ステータス管理やアラート機能が充実しているかを確認することが重要です。