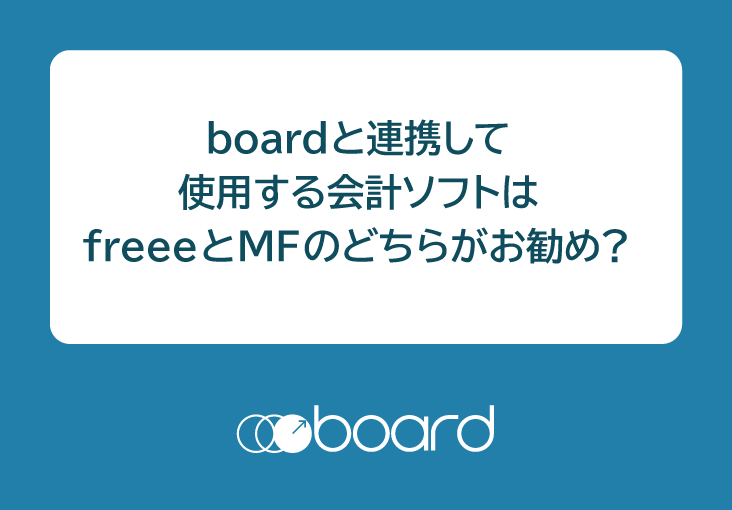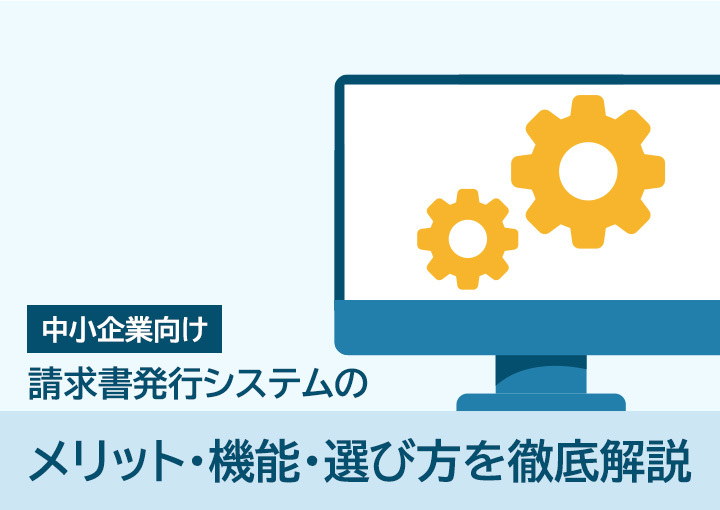近年は請求書をメールで送付する企業が増え、郵送に比べてコスト削減やスピードアップが図れるため、ビジネスの現場で広く利用されています。
本記事では、件名・本文の書き方(例文)、添付ファイルのファイル形式や命名、宛先の選び方、送付後の確認まで、実務で役立つポイントを分かりやすくまとめます。
目次
- メールで請求書を送る前に確認すべき基本事項
- 件名とメール本文の書き方
- 添付ファイルの扱い(ファイル名・フォーマット・パスワード)
- 宛先・Cc/Bccの運用ルール
- 一括送信とテンプレート活用
- 送付後の確認とフォロー
- よくあるトラブルとその対処法
- まとめ
メールで請求書を送る前に確認すべき基本事項
請求書をメールで送る前には、取引先の受け取り方針や社内ルールを確認することが大切です。特に以下の点は送付ミスやトラブルを防ぐために必ずチェックしてください。
取引先の受け取り方法
取引先がメール添付を許容しているか、郵送・専用のポータル・EDIなど特定の受け渡し手段を指定しているかを事前に確認します。指定がある場合は原則に従いましょう。
ただ、コスト削減や業務効率化の観点から、郵送からメール送付に切り替えたい場合は、取引先に相談してみるのも一つの方法です。相談してみると、意外と受け入れてもらえるケースもあります。
ファイル形式の確認
請求書のファイル形式は一般的にPDFが推奨されます。PDFは閲覧環境既存のレイアウト崩れが少なく、印刷・保存が容易なためです。わずかですが、ExcelやWordで提出するよう求められているケースはあるようです。
件名とメール本文の書き方
件名と本文は、受信者が内容をすぐに把握できるように簡潔かつ必要事項を含めて書きます。
件名の例とポイント
件名には、請求書の送付であることや、取引内容を特定できる情報を含めます。継続取引の場合は、件名に請求年月を入れるのも良いでしょう。
たとえば、以下のような件名が考えられます。
- 件名:請求書送付のご案内(○○○案件)
- 件名:請求書送付のご案内(2025年8月請求分)
件名に自社名や自分の名前のみを書くケースを見かけますが、一般的なメールサービスでは、送信元名は自動的に表示されるため、件名に差出人の情報を入れる必要はなく、請求書であることが分かる情報を入れる方が親切です。
メール本文に書くべき項目
本文には最低限、以下の情報を含めます。
- 送付の挨拶と送付物の明記
- 添付ファイルが複数ある場合はその内容
- 確認や不備があった場合の連絡方法
簡潔な本文の例:
いつもお世話になっております。
□□□合同会社の□□です。
2025年8月分の請求書を添付いたしましたのでご確認ください。
内容に不備がない場合はご返信は不要です。
よろしくお願いいたします。
添付ファイルの扱い(ファイル名・フォーマット・パスワード)
ファイル名の命名ルール
分かりやすいファイル名を付けることで、取引先側での管理や検索が容易になります。
- (自社名)_請求書_202508.pdf
- (自社名)_(取引先名)様_請求書_202508.pdf
ファイル名は、相手にとって親切なファイル名が望ましいです。ファイル名については「受領側が助かる請求書PDFのファイル名の付け方|送信者・受信者双方の視点から解説」にて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
複数の請求書を送る場合の扱い
請求書を複数送付する場合、いくつかのパターンが考えられます。
- 個別のファイルとして送付
- 1つのPDFにまとめて送付
- 合計請求書として送付
これらについては、どれが正解というより、取引先によって異なる可能性があります。事前に確認し、相手の希望に沿う形で送付しましょう。
参考:複数案件の請求書は個別に送付?合計請求書にまとめる?実務での最適な判断ポイント
パスワード付きZIPで送付する是非
取引先が社内セキュリティーの理由で暗号化やパスワード付きファイルを要求することがあります。従来からセキュリティー対策の1つとして広く利用されてきましたが、パスワード付きZIPは、受領側でマルウェア(ウイルス)チェックができないため、マルウェア拡散の温床になってきました。
そのため、昨今では、パスワード付きZIPのネガティブな影響の方が大きいとして、利用を控える企業が増えています。また、パスワード付きZIPの受領を拒否する企業もあります。パスワード付きZIPを利用する場合は、事前に取引先と合意の上で行うことをお勧めします。
宛先・Cc/Bccの運用ルール
宛先(To)
相手の担当者に送付するケースや、経理のメーリングリスト、受領請求書サービスのメールアドレスに送付するよう言われるケースなどがあります。
初めての取引の場合は、請求書の送付先を事前に確認するのが良いでしょう。
Ccの扱い
取引先から、「Toは担当者、Ccに経理」というように指定されることがありますので、その場合は、指定に従いましょう。
また、自社の運用ルールとして、「自社の経理のメールアドレスをCcに入れる」などのルールがある場合は、忘れずに入れましょう。
Bccの活用場面
送付した請求書をすべて手元に残すため、自社の記録専用のメールアドレスを入れる運用をするケースがあります。このような場合は、受取側には見えないBccが適しています。
一括送信とテンプレート活用
送付業務を効率化するために、テンプレートや差込機能を使うと入力ミスや抜け漏れを減らせます。また、クラウド請求書サービスやメール配信機能を利用すれば、一括送付が容易になります。請求書の送付の場合、一般的には定型的なメール文で送ることが多いため、テンプレート化が効果的です。
また、差込機能があるクラウド請求書サービスでは、それを使うことで一括送付をしつつ、より自然なメール文にできます。
送付後の確認とフォロー
送付漏れの確認
多くの場合、請求書の送付は月末月初にまとめて行うことが多いかと思います。ただ、現場の担当者への確認が遅れていたりすると、一部の請求書は同じタイミングで送付できないというケースもよくあります。
このように、送付タイミングが後になったものは、送付漏れが発生しやすくなります。そのため、送付漏れがないか確認できるよう、一覧の管理と送付有無のステータス管理を行うことをお勧めします。
ファイルの取得確認
送付後は、ファイルの取得確認ができると安心です。
クラウド請求書サービスでは、ファイルの取得状況を確認する機能があったりしますので、活用を検討しましょう。
未入金時のフォロー
期日を過ぎても入金がない場合は、まずは担当者に確認のメールや電話を行い、社内手続きや振込予定を確認します。定期的なフォローや督促テンプレートを準備しておくと対応が早くなります。
よくあるトラブルとその対処法
請求書のメール送付で発生しやすいトラブルと簡単な対処法をまとめます。
添付忘れ
送信直後に添付忘れに気づいた場合は、すぐに謝罪と正しいファイルを添付した再送メールを送ります。件名に「再送」や「添付忘れのお詫び」を明記しましょう。
間違った宛先に送信した
誤送信に気づいたら、速やかに受信者へ誤送信の旨を伝え、可能であればメール削除を依頼します。個人情報が含まれている場合は上長や情報セキュリティー担当に報告し、必要な対策を取ります。
まとめ
メールで請求書を送る際は、受け取り側のルールを確認し、件名・本文・ファイル名・宛先の運用を統一することが重要です。テンプレートや差込機能を活用し、送付後の確認や未入金フォローの仕組みを作ることで、業務の効率化とトラブル防止につながります。
請求書の送付はミスが発生しやすい業務です。小さな運用ルールを整備し、関係者に周知することで、スムーズなキャッシュフロー管理を実現しましょう。
また、クラウド請求書サービスを使うことで、本記事の多くのポイントを効率的に実現できます。詳しくは【中小企業向け】クラウド請求書サービス完全ガイド|導入メリット・注意点・選び方を徹底解説!をご覧ください。