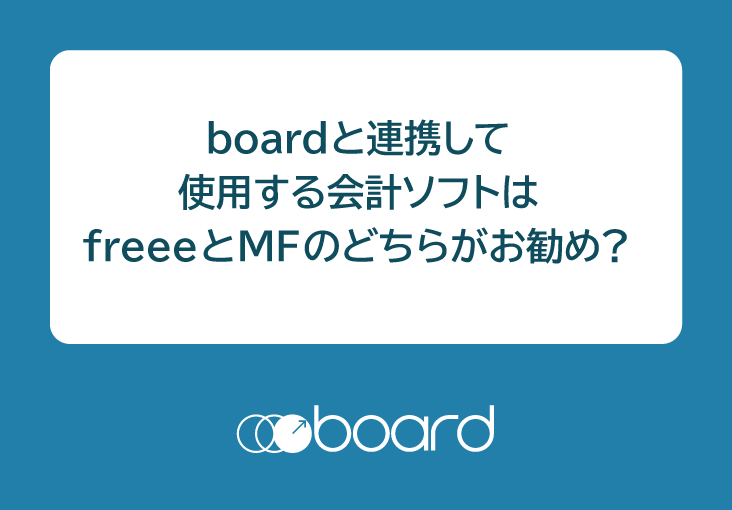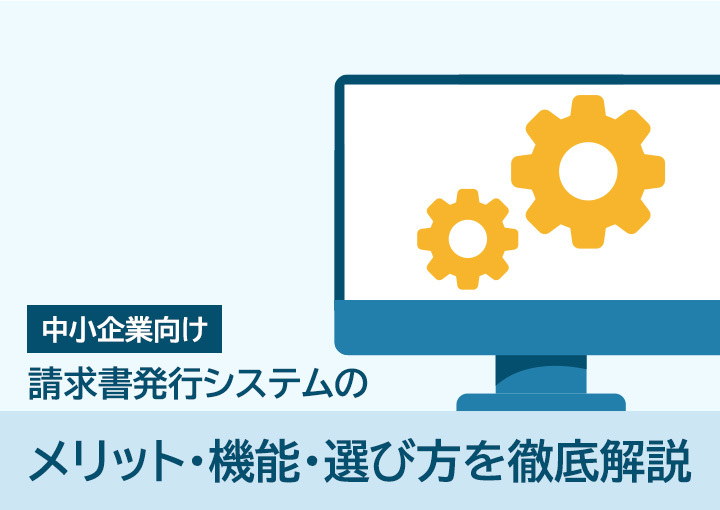請求書の送付方法は、顧客ごとに「メール」「郵送」「EDI」「受領システムへのアップロード」など様々あります。送付方法が多様だと業務が複雑になり、ミスやコスト増を招きます。
本記事では、管理方法と送付方法を減らす取り組みを実務目線で解説します。
目次
顧客ごとに送付方法が異なるときの課題整理
まず、送付方法が顧客ごとに異なることで起きる主な課題を整理します。課題を明確にすると、どの対策から手を付けるべきかが見えてきます。
たとえば、以下のような課題が考えられます。
- 管理工数の増加:送付手順が顧客ごとに異なるため、担当者の確認作業が増える
- ミスの発生:送付手段の間違いなどのヒューマンエラーが起きやすい
- コスト増:送付方法によっては、郵送費や封入作業などのコストや人手が必要になる
顧客ごとに送付方法を設定する運用設計
顧客マスター(取引先データ)に送付方法を登録・運用することで、送付時のヒューマンエラーを減らせます。実務で押さえるべきポイントを順に説明します。
取引先マスターへの属性追加
取引先情報に以下の項目を追加します。クラウド請求書サービスを使っている場合は、これらの項目が設定できるかを確認しましょう。
- 送付方法(メール / 郵送 / 受領ポータル / 受信用メールアドレス / 手渡し)
- 送信先メールアドレス
- 受領ポータルのURLまたはアップロード先ID
- 郵送先住所・宛名(郵送指定の場合)
- 備考(必須の添付物やファイル形式など)
請求一覧での絞り込み
請求一覧で「送付方法」ごとに絞り込みができると、まとめて処理したりチェックリストを適用したりできます。
- メール送付のみを検索して一括送信
- 郵送のみを検索して郵送処理
- 受領ポータル指定のみを検索・PDFダウンロードしてアップロード
顧客ごとに設定した送付方法ごとに絞り込みができると、それぞれの手段ごとに作業をまとめて行えるため、工数削減とミス防止に効果的です。
送付方法に応じたシステム活用(クラウド請求書サービスの活用)
多様な送付方法を一元管理するには、クラウド請求書サービスを活用するのが効果的です。ここでは導入時に見るべき機能をまとめます。
必須で確認したい機能
- 顧客マスターに送付方法とそのために必要な情報(メールアドレスや住所)を登録できること
- 請求一覧で送付方法で絞り込み・一括操作ができること
- メールテンプレート・差込機能・送信ログがあること
- 郵送代行や窓付き封筒対応があること
これらが揃うと、手作業が減り、送付方法ごとのオペレーションをシステムで統一できます。
受信用メールアドレスへの自動送付(アップロード代替)
受領ポータルに直接ログインして手動でアップロードする運用は手間がかかります。代替案として、受領側が受信用のメールアドレスを用意している場合、そのメールアドレス宛に請求書を送るだけで、受領システムに自動で反映される仕組みがあります。可能であれば以下を確認して依頼しましょう。
- 受領システムが受信用メール送信で自動連携できるか
- 自動連携時の件名や添付仕様(ファイル名や形式)
- セキュリティー上の制約(送信元ドメイン制限など)
この手法は手作業を大幅に削減できるため、業務改善効果が高いです。
送付方法の種類を減らすための実務的アプローチ
送付方法の種類を減らすと、全体の業務負荷とコストが下がります。昨今の世の中の流れに合わせた方向性で進めると、顧客側も受け入れやすくなります。
郵送をメールに切り替える
郵送からメールへの切替は、コスト面・効率面での効果が大きくぜひ取り組みたいテーマです。ただし、これまで郵送で行っていた場合は顧客側への確認が必要です。
詳しくは「請求書のペーパーレス化・電子化の方法とメリット|基礎からわかる電子請求書の活用」を参照してください。
郵送を継続する必要があっても、自分で印刷・封入・封緘するよりも、クラウド請求書サービスの郵送代行を利用する方が、ミスや手間が減ります。送付方法の管理と合わせて、「郵送で送る顧客で絞り込み→一括で郵送登録」とすることで、郵送業務の効率化が図れます。「請求書の郵送代行サービスのメリット」も合わせてご覧ください。
受領請求書サービスへのアップロードを受信用メールに変更してもらう
相手先が専用の受領ポータルを指定している場合、手動アップロードの手間が発生します。
しかし、多くの受領請求書サービスでは、受信用メールアドレスに直接送ればシステム側で取り込める仕組みを用意しています。この方法を使うと、手動アップロードの手間がなくなり、通常のメール送付と同じ運用にできます。
これにより、手動アップロードの手間が減るだけでなく、送付方法も「メール」になり、全体の送付方法の種類を減らすことができます。
まとめ
顧客ごとに請求書の送付方法が異なる状況は、管理工数やミス、コスト増を招きます。まずは取引先マスターへ送付方法を明確に登録し、請求一覧での絞り込みや送付ログの記録、テンプレート化で業務を安定化させましょう。
さらに、受信用メールの活用や顧客との段階的な切替交渉により、郵送など手間のかかる手段を減らすと大きな効果が得られます。