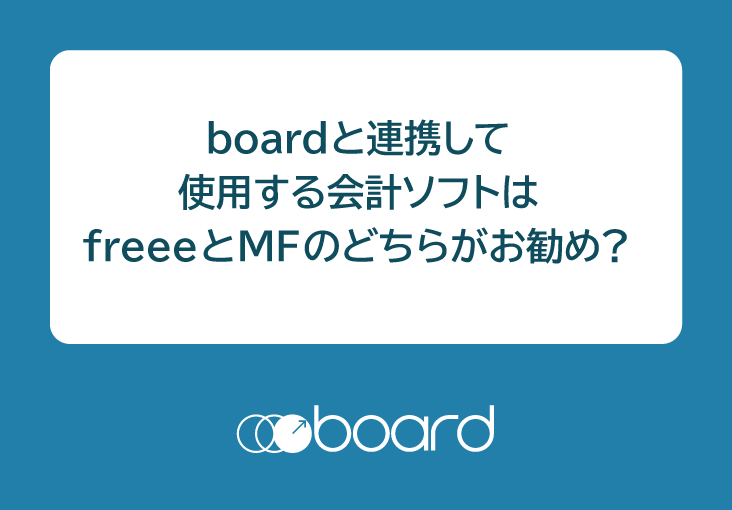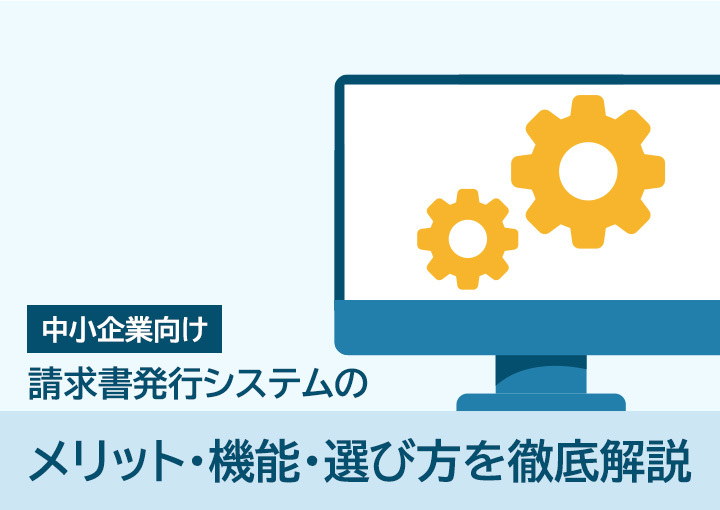コロナ禍で日本のビジネス界にも一気に定着した感のある電子契約ですが、boardにもDocuSign(電子契約の世界シェアNo.1)とクラウドサイン(電子契約の日本シェアNo.1)との連携機能が実装されています。今回は、電子契約サービス連携の使い方やメリットについて書いていきます。
税理士、業務設計士、リベロ・コンサルティング代表
金融のシステム企画部門、会計事務所、数社のスタートアップのバックオフィスを経て、独立。
既存の業務やシステムの使用方法を徹底的にヒアリングしながら、最適な業務フローとシステムの構成を設計し、業務からシステムまで再構築の実績多数。
業務設計の支援を手がけるリベロ・コンサルティング代表をメインで活動中。
1. 電子契約サービス連携で発注業務が電子化
クラウドサインがリリースされたのは2015年、DocuSignに至っては設立が2003年です。日本においても5年以上前から電子契約をすることは可能だったわけですが、法律や社内規定がまったく追いついておらず、発注書のやり取りについても「印刷→捺印→スキャンしてPDF化→メールで添付→後日、原本を郵送」という非常に面倒なプロセスが必要でした。これだけ手間がかかると、まだまだFAXが現役である理由もなんとなく理解できます。
しかし、弁護士ドットコム(クラウドサインの運営会社)の尽力もあり、電子契約の法的効力が認められ、2020年には日本においても一気に電子契約が市民権を得ました。とくに発注書のやり取りは、契約内容の法務チェックが不可欠である一般的な契約書と違って、「発注する意思を示す」ための署名・捺印なので、電子契約システムへの移行はどんどん進んでいます。
boardと二大電子契約システムが連携したことにより、「見積→発注→サービス提供→請求」という一連の処理がこれまで以上にスムーズに行えるようになりました。単にboardから発注書のデータを契約システムに連携するというだけでなく、契約完了を受けて受注ステータスを「受注済」にするなど、boardと電子契約システムがAPIを介して一体として機能するように設計されています。
FAX、ハンコ、そしてExcel。SaaSやAPIという概念がなかった時代に管理業務の中心にあった仕組みがいつまで経ってもなくならないのは、技術的な問題ではなく、今よりも圧倒的に簡単で便利になるという実感を得られない人が多いからだと思います。電子契約の有効性が一定レベルまで浸透した今、次に重要なのは、その前後の処理との連携がスムーズにできるかどうかです。
board・freee連携と同様に、この連携機能は最初にAPI連携の設定さえしてしまえば、それ以降は非常にスムーズに動いてくれるため、シンプルで使いやすく、boardユーザーにとってなくてはならない機能になりそうです。
2. boardの強み
boardは「案件」という枠組みの中で、見積や発注、請求という一連の処理が発生するという考え方で作られています。他の帳票作成ツールでは単に見積書を請求書に変換するような設計になっている中で、boardの設計思想はかなり秀逸です。見積書を作成する、請求書を作成する、というように点で捉えた要件に対応するのではなく、案件管理業務を「見積→発注→請求」という線で捉えた上で、必要な機能を実装しているのです。
一方で、請求書を発行すれば当然に入金管理もしなければいけませんし、会計上の売上計上もしなければいけません。しかし、さすがにこれらはboardよりも会計ソフトの方が得意な領域ですし、ここまで実装してしまうと開発やメンテナンスが非常に重たくなります。「ベスト・オブ・ブリード」、日本的に言うなら「餅は餅屋」という考え方ですが、boardは案件管理領域に特化して機能に磨きをかけるからこそ、使い勝手の良いツールであり続けることができるのです。
今回の電子契約システムとの連携でも、この思想は貫かれています。電子証明書の機能や発注処理のためのワークフロー機能を作ろうと思えば作れるかもしれませんが、すでに世の中で広く使われている電子契約システムがあるのであれば、それと連携することで業務全体の効率化を実現する方を選ぶのがboardなのです。
その代わり、連携する項目のマッピングはもちろん、設定の手順やヘルプページのわかりやすさなどは徹底的に考え抜かれています。boardを導入する規模の企業では、エンジニアや情シス専任担当者がいない場合も多いと思いますが、ITリテラシーが高くないバックオフィスや営業の人でもほとんど迷うことなく連携できます。
いわゆるCRMツールは、案件管理は強いですが、帳票作成機能が実装されていないものがほとんどです。一方で帳票作成ツールは、前述の通り案件管理の概念を持っていません。案件管理がきちんとできて、帳票もしっかり作れて、という毎月数十件の案件を管理する中小企業のニーズにちょうどフィットするのがboardというツールです。
そういう企業にとって、シンプルで使いやすい電子契約連携の仕組みがあれば、「見積→発注→請求」の処理フローを非常にスムーズに構築できます。発注書のやり取りについて、今後はどんどん電子契約システム上の処理が増えていくことが確実な中で、boardがクラウドサインとDocuSignとの連携に対応したということは、中小企業にとって心強いニュースになるのではないでしょうか。
3. 電子契約連携の使い方
連携の設定方法についてはDocuSign、クラウドサインともにヘルプページに画面のスクリーンショットつきで丁寧に解説されているので、ここではこの機能を使う場面について少しだけ解説します。
boardで案件を作成し、先方に見積書を共有した後、「発注したい」となった際にやり取りするのが発注書です。このタイミングで電子契約連携の設定をしていれば、boardの書類編集画面の右下に「電子契約サービス連携」のボタンが表示されます。そこから発注書、発注請書、発注書&発注請書のいずれかを選択して、電子契約への書類(PDF)の連携を行うことができます。

連携された書類への署名欄や押印欄等の追加は電子契約サービス側で実施します。なお、原則として電子契約サービスには「下書き(ドラフト)」状態で連携されますが、クラウドサインについては、board側で宛先(メールアドレス)情報を入れて、直接送信することも可能です。
これまでboardでPDFを作成し、ダウンロードして、電子契約サービスにアップロードしていた処理手順がboard側の処理だけで完結するので、とても楽になったと感じられる方が多いはずです。
また、電子契約の締結が完了したらboardの受注ステータスを「受注済」にするなどの設定も可能です。board側のステータスが発注状況と正確に連動するので、受注管理をしている担当者にとっては待望の機能だと思います。
以上、非常にシンプルではありますが、これがboardの電子契約連携の使い方です。シンプルだからこそ使いやすくて、パワフルな機能だと思います。とくに発注処理が煩雑だと感じている企業の方は、board&電子契約を導入するだけで大幅な業務効率化が実現できると思いますので、ぜひ試してみてください。